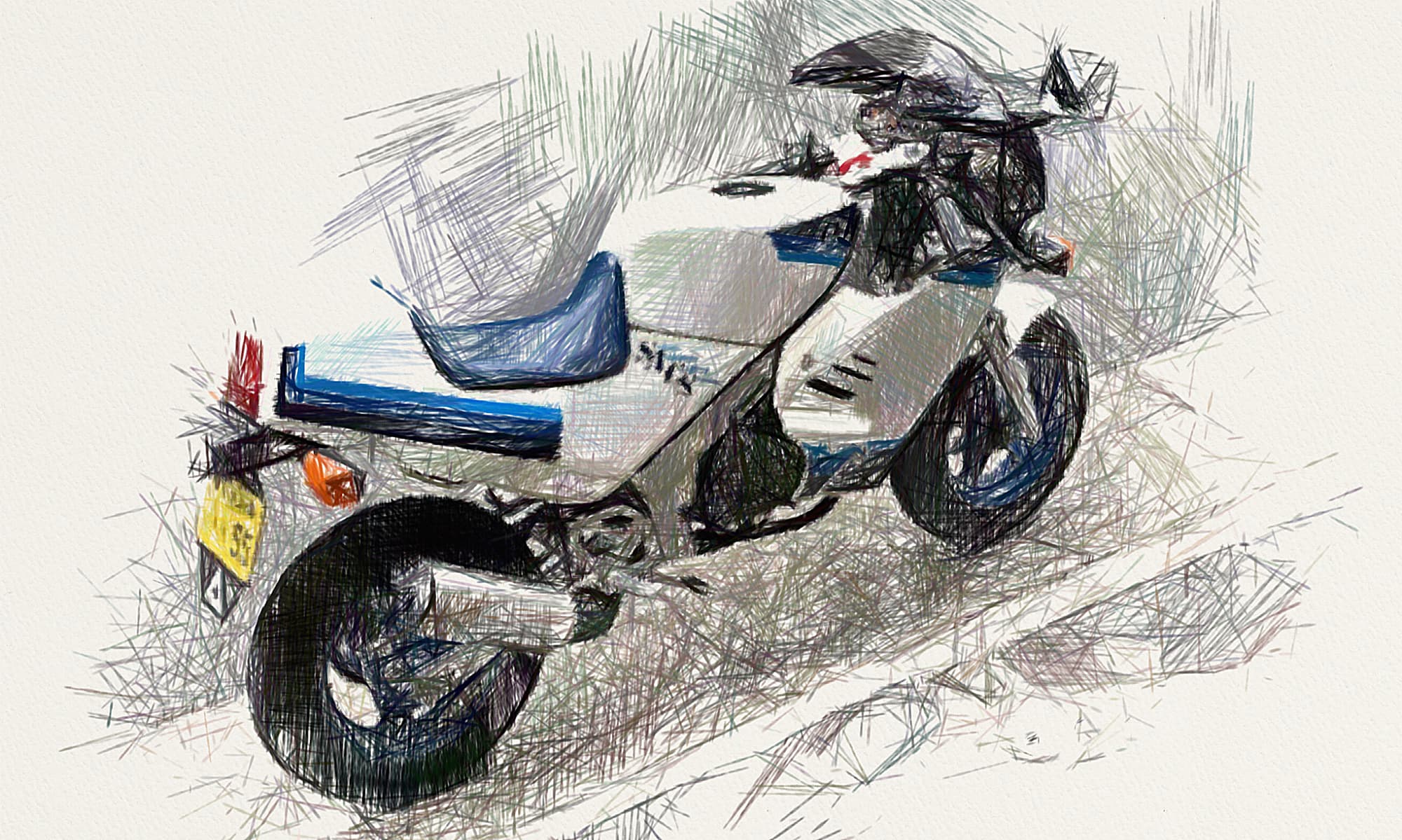MEADE ETX-90に付ける直焦アダプターを買って月や惑星を撮影してみようと思っていた。
参考になるようなWebやYouTubeを観ているときに“LensKing’s TV Bosque Rico”という日本人の男性が“ある天体望遠鏡”を熱く語っているのに出くわした。
ETX-90と同じマクストフカセグレイン式の天体望遠鏡だ。その望遠鏡の口径は127mmある。
思い返してみる今使っているMEADE ETX-90ECの発売年は1999年だった。もう20年以上昔の機器なのだ。iPhoneが発売される以前のマクストフカセグレイン式望遠鏡である。
私は新品で買ったわけではないが、新品の価格は125,000円(定価)でコントローラーが30,000円だった。
日時の記憶はないが、たまたま大阪に出かけた帰り道に奈良市のお宝倉庫のショーケースの中で新品同様のMEADE ETX-90ECJが置いてあり、これを見つけた途端に“おいでおいで”をしているように思ったので救出してきたのだ。
価格も30,000円以下だったような記憶がある。
2007年には撮影したデータが残っているので2007年以前ということだ。
昔の望遠鏡と言えば、精密に機械仕上げされた赤道儀にレンズや反射鏡を取付けた望遠鏡というのが当たり前だったが、近年は自動追尾してくれる電子機器の様相を呈していた。
ETX-90ECはコントローラーで星を自動で導入できる機種だったのだ。
その頃から20年以上経過した現在、新しい望遠鏡をWebで何度も観ているとだんだん欲しくなったではないか。
Webで見つけた“Sky-Watcher MAK127 VIRTUOSO GTi”を検索していると、鏡筒を固定しているアリガタが長いので前後に位置調整が出来るし、トドメはこのサイトに“アイピースアダプターの末端にはM42 P0.75のネジが切られていて、一般的なTリングを介してカメラの取付が可能”と書かれていたのでTリングを取付ければNIKONのデジタルカメラやm4/3のカメラを取付られる。
(ETX-90の鏡筒に付いていたネジは特殊なサイズとピッチのネジだった)
楽天市場やAmazonで“Sky-Watcher MAK127 VIRTUOSO GTi”を検索していると7万6千円〜9万円ほどの価格で売っているが、楽天市場のシュミット(アウトレット)ではなんと54,800円で売っているではないか。
(後で分かったことだが箱が少しだけ傷んでいただけらしい)
更に楽天のポイント利用すると-2,021円。
支払総額は52,779円😅
で?
もちろんポチったのは言うまでもない。
<鏡筒の主な仕様>
・光学形式:マクストフカセグレン式反射望遠鏡
・有効口径:127mm
・焦点距離:1,500mm
・口径比:1:11.8
・極限等級:12.3等
・集光力:329倍
・ファインダー:レッド・ドット・ファインダー
・鏡筒質量:約3.6kg(アイピース除く)
・セット品総質量:約8.2kg(電池、アイピース除く)
・付属品:アイピース(10mm、25mm)、90°天頂ミラー
<VIRTUOSO GTi(ヴィルトオーソ)の主な仕様>
・最大搭載可能重量:約6kg
・本体質量:約4.7kg(電池除く)
・電源:DC12V (単三形乾電池×8本)
・駆動:DCサーボ モーター
・駆動スピード:恒星時~800倍速
・追尾モード:恒星時追尾,月追尾
・データベース:固有名がついた恒星、二重星、メシエ,NGC,IC,Caldwellの各カタログ天体
・SynScan Pro App対応OS:iOS(iOS8.0以降のiPhone,iPad,及びiPod touchに対応)、Android OS